
今日までの旅メーター
訪れた政令指定都市の区の数 【87/171】
訪れた旧市町村の数【1546/2,097】総計【1633/2,268】スーパーカブの総走行距離
39087km
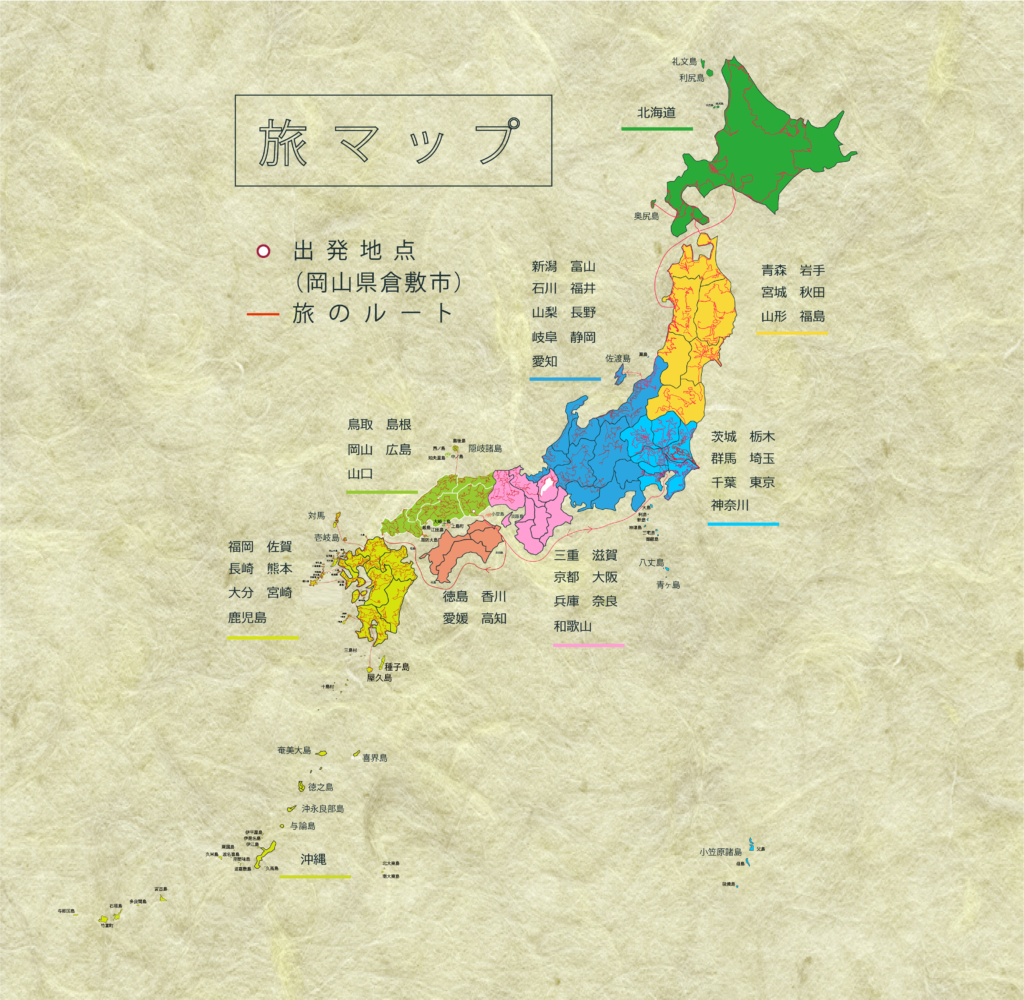
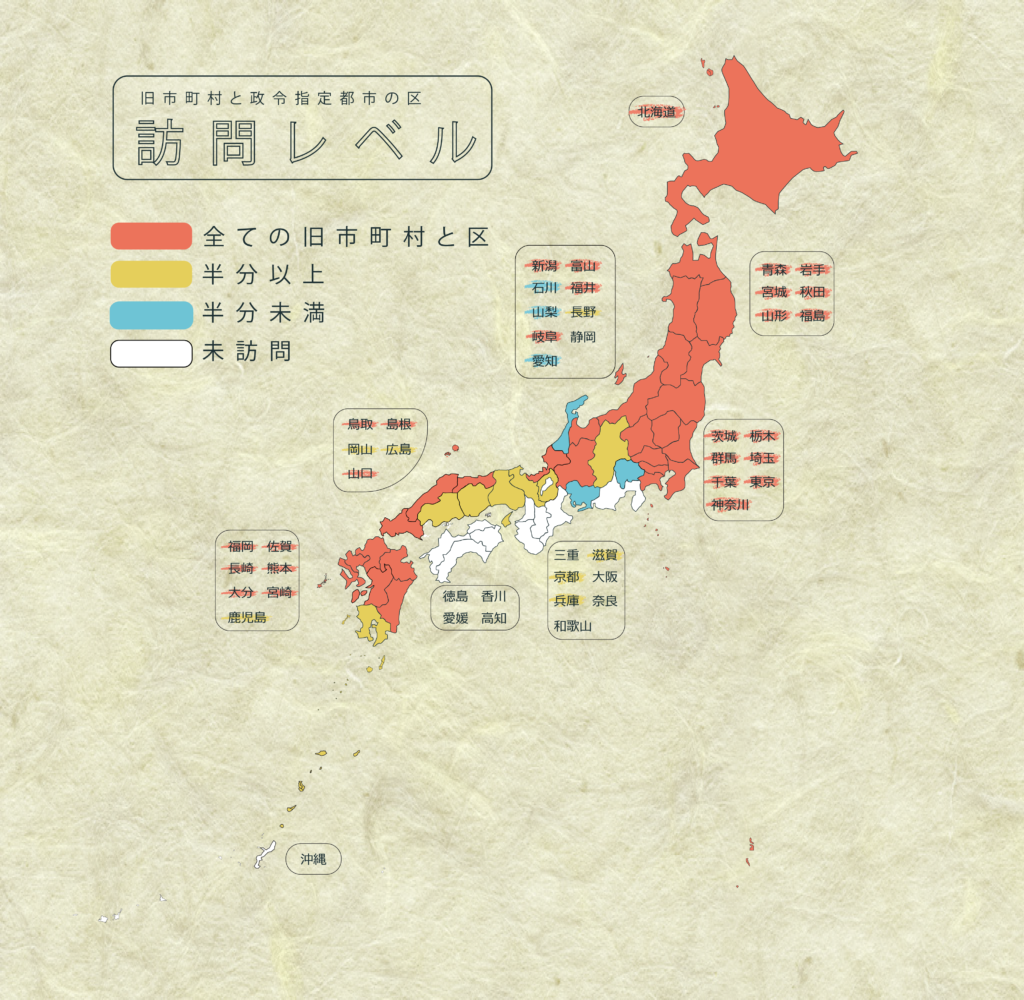

今日の旅先のこと
今日がどんな日だったかまとめるならば、「晴れあり風あり雷雨あり」に尽きます。長野県の旅も最終盤ですが、簡単ではないな、という気持ちになりました。焦らず踏ん張る気持ちで、予定通りの行程を進めてよかったです。松本市から塩尻市、そして木曽路へ。それでは振り返っていきましょう。
旧波田町(松本市)(1/6)
朝8時過ぎに松本市街地を出発しました。どんよりした曇り空で、風が強い。天気予報のレーダーも見て、雨が降るのも時間の問題だろうと、最初から合羽と長靴を身に付けての出発です。
旧波田町へ向かっていく途中も、山の方では明らかに白い霧のようになっていて、あれは雨だろうと。そこに向かっていくので、やっぱり雨が降りはじめます。田んぼの道は風がかなり強く、いきものがかりの「風が吹いている」も脳内で流れました。
さて、波田支所の近くには松の木が立派な小学校があり、さらに坂を登った先に波田駅と住宅地が広がっていました。雨も降る静かな日常。波田駅は松本電鉄上高地線で、こんな路線があるのだなあとも。
旧波田町(松本市)(1/6)
朝8時過ぎに松本市街地を出発しました。どんよりした曇り空で、風が強い。天気予報のレーダーも見て、雨が降るのも時間の問題だろうと、最初から合羽と長靴を身に付けての出発です。
旧波田町へ向かっていく途中も、山の方では明らかに白い霧のようになっていて、あれは雨だろうと。そこに向かっていくので、やっぱり雨が降りはじめます。田んぼの道は風がかなり強く、いきものがかりの「風が吹いている」も脳内で流れました。
さて、波田支所の近くには松の木が立派な小学校があり、さらに坂を登った先に波田駅と住宅地が広がっていました。雨も降る静かな日常。波田駅は松本電鉄上高地線で、こんな路線があるのだなあとも。










また、波田扇子田運動公園にも行ってみたのですが、工事中で車はたくさん停まっているけれど人の気配があまりなく、今回はスッと離れました。



松本市(2/6)
松本市街地で目指す場所は、やっぱり松本城。前回の旅では、「松本市」というひとつの括りで「上高地」を訪れたので、松本城には訪れていません。なーんだ、行ったことないんだ? はい、そうなんです。見たことはありますが、お城には入ったことがなくて。
まずは市街地へ。松本駅の周辺は東京のような均一感があって、松本城側は松本の市街地、という感じがしました。パルコあたりが、境界線かなあと。
松本市街地で目指す場所は、やっぱり松本城。前回の旅では、「松本市」というひとつの括りで「上高地」を訪れたので、松本城には訪れていません。なーんだ、行ったことないんだ? はい、そうなんです。見たことはありますが、お城には入ったことがなくて。
まずは市街地へ。松本駅の周辺は東京のような均一感があって、松本城側は松本の市街地、という感じがしました。パルコあたりが、境界線かなあと。





そして、いざ松本城へ。さすがは国宝。警備員も多ければ、観光客も多く。海外の人も多かったし、団体の修学旅行生も来ていました。なので、国宝・松本城内へ入ったものの、天守へ登るには大渋滞。これは、相当待つかもしれないなあと思って、途中抜けのルートを使わせてもらいました。え、天守まで行かないの? 行かないんです。再訪するという宿題が増えましたね。





塩尻市(3/6)
次にやってきたのは、塩尻市です。まずは市街地へ。途中の国道は郊外の雰囲気でした。そして、目的地に着く頃には正面から明らかに雨雲が迫っており、太陽が隠れると急に寒くなります。やがてザッと雨も降ってきて、これは万事休すか、と思ったら、ほんの少し外れたみたいで、また日差しが戻ってきて。どっちの天気なんだと不思議に感じながらの散策でした。ハロウィンのおまつりがあるみたいで、週末に歩行者天国になるというポスターも。いいですねえ。
次にやってきたのは、塩尻市です。まずは市街地へ。途中の国道は郊外の雰囲気でした。そして、目的地に着く頃には正面から明らかに雨雲が迫っており、太陽が隠れると急に寒くなります。やがてザッと雨も降ってきて、これは万事休すか、と思ったら、ほんの少し外れたみたいで、また日差しが戻ってきて。どっちの天気なんだと不思議に感じながらの散策でした。ハロウィンのおまつりがあるみたいで、週末に歩行者天国になるというポスターも。いいですねえ。








その後、「平出遺跡」という縄文時代から平安時代にかけての集落跡へ向かいました。ここではむしろ日差しと青空が戻って、山にかかる分厚い雲が綺麗で。今日の天気は現場でしかわからないなあ、ともはっきり思いました。





旧楢川村(塩尻市)(4/6)
塩尻市街地から、南東へ向かうと諏訪方面に、南西方面に向かうと木曽路に入っていきます。今回は木曽路を目指すので、南西の方角へ。徐々に山が近づき、周囲の気配も一気に山らしく。
そして、奈良井宿を散策しました。もし時間があれば、奈良井宿の手前にある平沢(市街地)も歩きたかったです。通過していくときの住宅街の様子が、印象的だったから。
ただ、あれだけ晴れた青空もサッと消えてしまい、奈良井宿に着くと少しずつ雨もパラパラと戻ってきて。駐車場から往復したのですが、かなり長い宿場町だと感じました。全長は約1kmあるようです。1kmも町並みが続くのだから、相当すごいなと。そば、五平餅、木工細工、漆の器、などなど、いろんなお店がありました。ちなみにこれまでに長いなと思った中津川市の「馬籠宿」も、600mほどでした。往復すれば800m違いますからねえ。
塩尻市街地から、南東へ向かうと諏訪方面に、南西方面に向かうと木曽路に入っていきます。今回は木曽路を目指すので、南西の方角へ。徐々に山が近づき、周囲の気配も一気に山らしく。
そして、奈良井宿を散策しました。もし時間があれば、奈良井宿の手前にある平沢(市街地)も歩きたかったです。通過していくときの住宅街の様子が、印象的だったから。
ただ、あれだけ晴れた青空もサッと消えてしまい、奈良井宿に着くと少しずつ雨もパラパラと戻ってきて。駐車場から往復したのですが、かなり長い宿場町だと感じました。全長は約1kmあるようです。1kmも町並みが続くのだから、相当すごいなと。そば、五平餅、木工細工、漆の器、などなど、いろんなお店がありました。ちなみにこれまでに長いなと思った中津川市の「馬籠宿」も、600mほどでした。往復すれば800m違いますからねえ。









また、建物にもどこか入ってみようと、「上問屋資料館」に入館してみました。やはり館内は長細く、趣たっぷりでカッコよくて。明治天皇が昼食を召し上られた部屋も残されていました。








再び駐車場に戻ってきた頃にはかなりの本降りの雨模様で、これまで脱いでいた合羽をもう一度着て、再出発です。
旧日義村(木曽町)(5/6)
さあ、ここから木曽町に差し掛かっていくところで、土砂降りに変わりました。土砂降りに変わると、視界が見えづらい。ぼくのヘルメットはフルフェイスじゃないので、大きな雨粒だとかなり顔に当たるのが痛い。スピードも落ちるので、後続車に良いタイミングで抜いてもらわないと危なくなる。と、いろいろ集中する必要があります。
かろうじて旧日義村の日義支所に着くと、屋根付きの駐輪場があったので雨宿りしました。すでにずぶ濡れだけれど、屋根付きの駐輪場は天国に感じます。
たぶん、20分ぐらいは休んで、それから少し小雨になったときに、支所の周辺も散策しました。それから木曽福島へ向かう途中、「道の駅 日義木曽駒高原」にも立ち寄って。風がすごく強くて、木から一斉に落ち葉が飛び交い、激しい天気だと感じながら。
旧日義村(木曽町)(5/6)
さあ、ここから木曽町に差し掛かっていくところで、土砂降りに変わりました。土砂降りに変わると、視界が見えづらい。ぼくのヘルメットはフルフェイスじゃないので、大きな雨粒だとかなり顔に当たるのが痛い。スピードも落ちるので、後続車に良いタイミングで抜いてもらわないと危なくなる。と、いろいろ集中する必要があります。
かろうじて旧日義村の日義支所に着くと、屋根付きの駐輪場があったので雨宿りしました。すでにずぶ濡れだけれど、屋根付きの駐輪場は天国に感じます。
たぶん、20分ぐらいは休んで、それから少し小雨になったときに、支所の周辺も散策しました。それから木曽福島へ向かう途中、「道の駅 日義木曽駒高原」にも立ち寄って。風がすごく強くて、木から一斉に落ち葉が飛び交い、激しい天気だと感じながら。









旧木曽福島町(木曽町)(6/6)
最後に向かったのは、旧木曽福島町です。中山道の福島宿を中心に散策しました。前回の旅では国道の近くから眺める形で撮影したけれど、今度はまちを歩きたいと。土砂降りだったわけですが。
でも、雨の中の宿場町も風情があるなあとすごく感じました。というのも、江戸時代に中山道を歩いた人たちも、毎日が晴れていたわけではないだろうし、今日みたいな土砂降りの日だってあっただろうと。そして、ぼくはいま合羽を着て歩いているけれど、風で飛ばないようにフードを片手で持って、雨風が強いので前傾姿勢になって歩いている姿勢は、土砂降りの道を歩く江戸時代の人たちと似ているかもしれないなあ、と思えたわけです。そう思うと、とてもありがたい体験でした。
最後に向かったのは、旧木曽福島町です。中山道の福島宿を中心に散策しました。前回の旅では国道の近くから眺める形で撮影したけれど、今度はまちを歩きたいと。土砂降りだったわけですが。
でも、雨の中の宿場町も風情があるなあとすごく感じました。というのも、江戸時代に中山道を歩いた人たちも、毎日が晴れていたわけではないだろうし、今日みたいな土砂降りの日だってあっただろうと。そして、ぼくはいま合羽を着て歩いているけれど、風で飛ばないようにフードを片手で持って、雨風が強いので前傾姿勢になって歩いている姿勢は、土砂降りの道を歩く江戸時代の人たちと似ているかもしれないなあ、と思えたわけです。そう思うと、とてもありがたい体験でした。













というわけで、今日の散策はここまで。最後に旧日義村の宿で一泊しました。周辺にお店がないので夕食付き。おしゃれな空間だったので、あれ、今日ってどんな日だったっけ、と。

本日のひとこと
合羽、長靴、服、カバンカバー、いろんなものを干す夜です。
合羽、長靴、服、カバンカバー、いろんなものを干す夜です。
旅を応援してくださる方へ
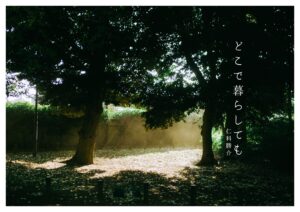
今回の旅をはじめる前に、自費出版の写真集「どこで暮らしても」を製作しました。東京23区を1200kmほど歩いて巡り、撮影した一冊です。売り上げは旅の活動費として、活用させていただきます。
写真集の商品ページはこちら
(終わり。次回へ続きます)
写真集の商品ページはこちら
(終わり。次回へ続きます)
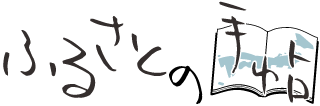










LEAVE A REPLY